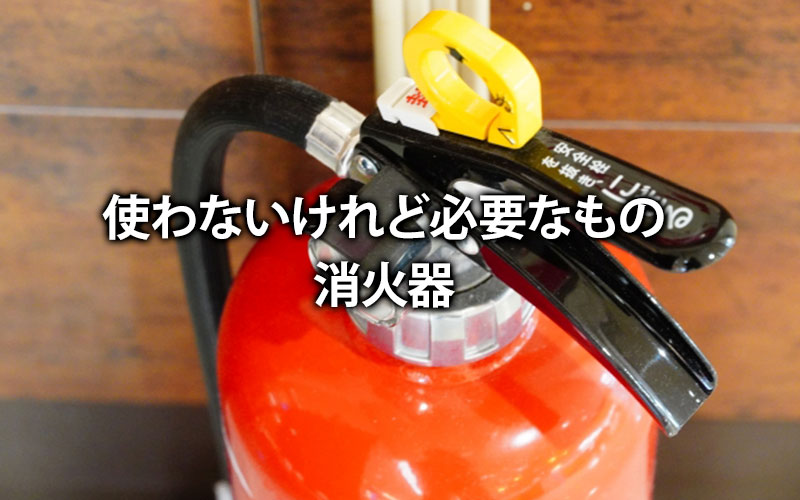職場の災害対策
9月になると、多くの企業や自治体で防災訓練が行われます。
これは1923年9月1日に発生した関東大震災に由来しており、この日が「防災の日」と定められているためです。
日本は昔から地震と向き合ってきた国です。
ここ30年ほどの間でも、阪神・淡路大震災、新潟県中越地震、東日本大震災、熊本地震、そして昨年1月の能登半島地震と、大きな地震が繰り返し発生し、想定を超えるような被害がたびたび生じています。
今後30年以内に80%の確率で発生するとされる南海トラフ地震についても、広い範囲で甚大な被害が想定されています。
残念ながら、日本中どこにいても、地震の危険から逃れることはできないようです。
防災訓練・体験
防災訓練は、こうした災害に備えるための大切な取り組みです。
たとえば「自分がどこへ避難すればよいのか」と問われて、すぐに答えられる人は案外少ないのではないでしょうか。
まずは、自治体が用意している防災マップで避難場所を確認しておきましょう。
そして、自宅や職場など普段いる場所から避難場所まで実際に歩いてみるのも大切です。
思ったよりも遠い、危なそうな道があるなど、歩いてみると注意すべき点が見えてきます。
災害時には家族や職場と連絡をとりたくても、電話がつながりにくくなります。
そんなときの連絡方法のひとつとして、「災害伝言ダイヤル171」があります。
出張先で被災したときなどにも頼りになりそうです。
災害伝言ダイヤルはNTT東日本、NTT西日本などの通信事業者が共同運営しているもので、毎月1日と15日に体験利用ができますので、防災訓練の一つとして取り組んでみるのはいかがでしょうか。
NTT西日本「災害用伝言ダイヤル(171)」https://www.ntt-west.co.jp/dengon/
※他の通信事業者でも171の利用方法は同じです。
職場に必要な備えは?
家庭だけでなく、職場での備えも欠かせません。
平日の昼間に大地震が起きれば、多くの人が勤務先にいることになります。
ヘルメットや防災頭巾は手の届くところに置いてあるでしょうか。
水や食料の備蓄は人数分、数日分揃っているでしょうか。
簡易トイレやラジオ、懐中電灯もすぐに使える状態にしておく必要があります。
準備をしているつもりでも、実際に点検してみると電池が切れていたり、保存食の賞味期限が過ぎていたりするものです。
備蓄は「そろえて安心」ではなく「定期的に見直してこそ安心」だと言えるでしょう。
市販の防災セットを活用し、数年ごとに丸ごと入れ替えるようスケジューリングしておく方法もあります。
さらに、災害時に自分たちがどのように行動するのかをあらかじめ想定しておくことも大切な備えです。
避難するのか留まるのか、交通機関が止まったらどうするのかなど、いざというときになって冷静に判断をするのは難しいものです。
職場での防災訓練の際には、行動方針を考え、お互いに共有しておくことも推奨されます。
BCPはできていますか?
そしてもう一つ、職場における災害対策を語る上で欠かせないのが、BCP(事業継続計画)の視点です。
BCP(Business Continuity Plan)とは、大規模災害のような不測の事態が発生しても、事業を止めない、あるいは早期に再開できるようにするための計画のことを指します。
帝国データバンクの2025年の調査によれば、BCPを策定している企業は全体の20.4%に過ぎません。
大企業では38.7%に達していますが、中小企業では17.1%にとどまり、必要性を感じながらも「人手が足りない」「コストをかけられない」といった理由で後回しになっているのが現状です。
しかし事業の継続性は取引先や顧客の信頼を守ることにつながり、同時に従業員の安心感を支えるものでもあります。
規模の大小にかかわらず、少しずつでも取り組む価値のある課題だと言えるでしょう。
災害は、いつ起こるか分かりません。
この9月、防災月間をきっかけに、改めて「職場の災害対策」について考え直してみてはいかがでしょうか。
防災・減災の視点から設計や図面の検証をお考えの事業所様、企業様、BIMの業務委託を検討してみませんか。
Building Information Modeling 株式会社では、業務委託を専門としております。
BIM、積算の分野でお困りのことがありましたら、ぜひお声をおかけください。